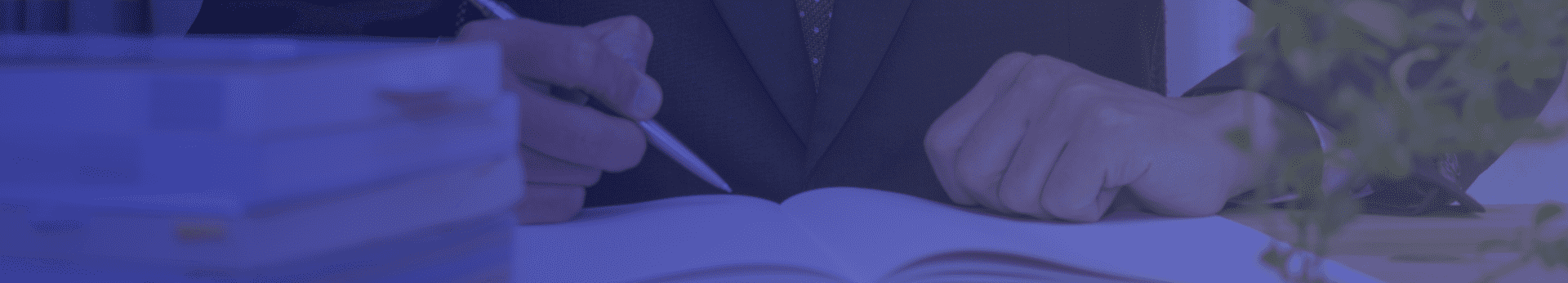
弁護士コラム
第153回
『【弁護士による回答】内定辞退に退職代行が使える理由』について
公開日:2025年8月25日
退職
弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。
退職代行を専門的にはじめて早いもので、数年が経ちました。
その間、数多くの退職代行をした経験から「これは」と思うことをコラムにします。
コラム第153回は『【弁護士による回答】内定辞退に退職代行が使える理由』についてコラムにします。
※弁護士清水隆久が読売新聞で内定辞退について解説しています。
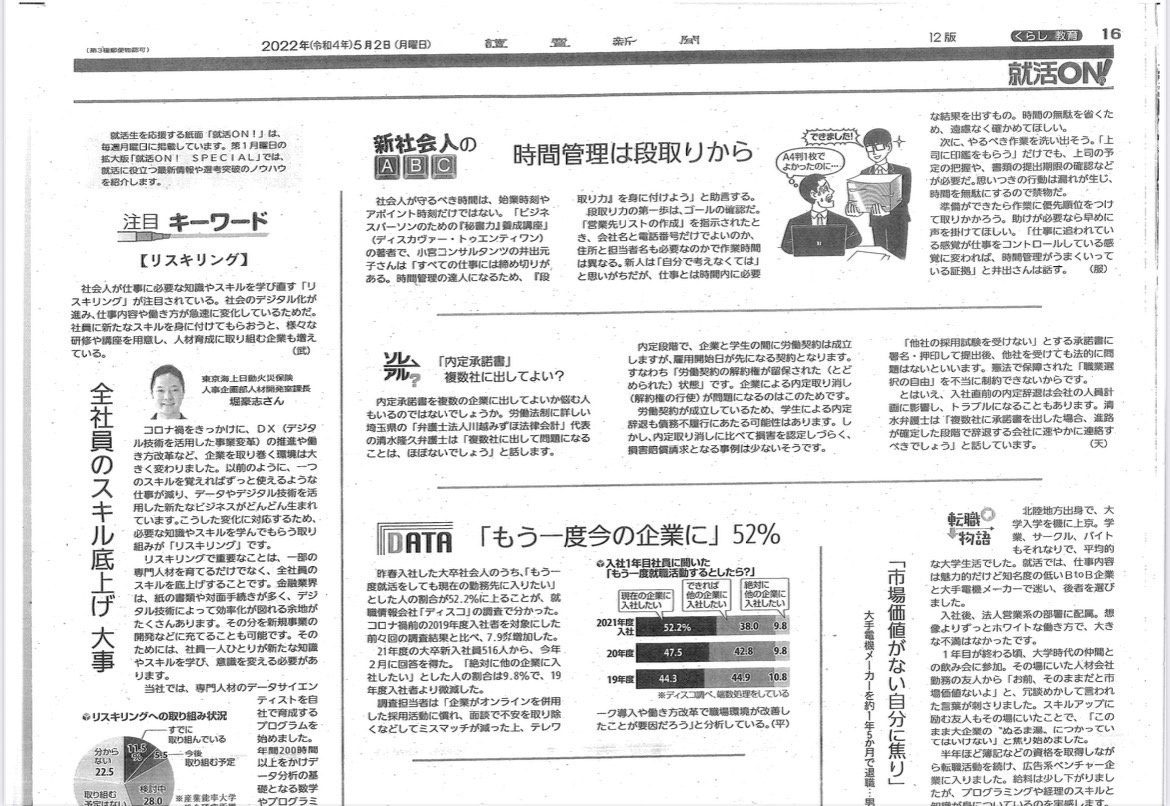
内定辞退代行の相談や依頼については、弁護士の退職代行からお問い合わせください。

目次
1.内定辞退代行について
最近では内定辞退を退職代行にて辞退する依頼が増えています。内定辞退が可能な場合を解説しつつ退職代行を使う有効なケースを解説していきます。今回のコラムについても弁護士の清水隆久が解説します。
内定の法的性質は、「始期付解約権留保付労働契約」であると解されています(最高裁昭和54年7月20日判決)。内定とは、「労働契約」であって、内定の時点で労働契約が成立するのがポイントです。「始期付」とは、契約成立日とは別に契約開始の時期が定められていることを意味します。
労働契約が成立しているのであれば、辞退というのは法律的には不正確な表現であって、『その会社を退職すること』にあたります。退職するということは、皆さんの予想通りだと思いますが、退職代行を使うことができます。
そこで、まず、第一のポイントとしては、内定を辞退するために、退職代行サービスを利用することができます。
では、内定辞退をするのは、何日前にすることができますか?というご質問をいただきますが、この答えは、『いつでもできます。』
なぜなら、内定辞退は、退職代行そのものだからです。入社前でも入社後でも、退職代行の内容自体に変わりはありません。
退職代行業者のコラムで、14日前に言うことを推奨していましたが、14日前にこだわる必要はありません。入社してからも退職している方はたくさんいるはずです。
おそらく民法第627条第1項によれば退職は、申し出をしてから14日経過後になっているため、その民法第627条第1項を根拠としていますが、内定辞退の日にちのリミットにはなりません。また、事前に内定承諾書を出した場合や、内定確定書を出した場合でも、内定辞退をすることは可能です。
そこで、第二のポイントとしては、内定辞退ができる時期には制限がありません。いつでも内定辞退ができます。次のポイントとしては、仮に、雇用の定めのある雇用契約、例えば、契約社員を前提として内定を受けた場合には、気をつけなければなりません。
雇用契約の定めがあった場合には、退職するためには、『やむを得ない理由』が必要となります(民法第628条)。内定辞退の法的性質は繰り返しますが、雇用契約の解除、すなわち、退職そのものとなります。
したがって、内定辞退=退職であるため、内定辞退には、やむを得ない理由が必要になります。やむを得ない理由については、コラム第129回『期間の定めのある雇用契約と退職代行』について、ご参照ください。
第三のポイントとしては、契約社員の内定辞退の場合には、注意が必要となります。必ず弁護士にご相談することをお勧めします。内定辞退ができないケースがあります。お困りでしたら、私までご相談ください。力になります。
最後に、内定承諾を出していた場合でも、なぜ内定辞退ができるかについて簡単に解説しますと、『内定承諾にあたって、内定辞退をしません』と承諾していたとしても、退職する権利を害する規定となり、公序良俗に反し無効となります(民法第90条)。
したがって、内定承諾書を提出していた場合でも内定辞退することに制限はありません。
2.補足(損害賠償について)
内定辞退にあたっても損害賠償が発生する可能性はあります。内定辞退に伴う損害賠償についても、コラム第115回『損害賠償対応プランと退職代行がおすすめな理由【人員要件】』について、をご参照下さい。
弁護士法人川越みずほ法律会計の紹介
いち早く退職代行を手掛け、今までも多数の相談及び解決事例があります。
今回、その中でもご質問が多いご相談事項をコラム形式でまとめました。
この記事の執筆者

弁護士清水 隆久
弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士
埼玉県川越市出身
城西大学付属川越高校卒業、中央大学法学部法律学科卒業、ベンチャー企業経営、労働保険事務組合の理事、社会保険労務士事務所の代表を経て、予備試験合格、司法試験合格、司法修習終了後、弁護士法人川越みずほ法律会計を設立、同弁護士法人代表に就任。労務・税務・法律・経営の観点から、企業法務に関わる傍ら、東から西へと全国を飛び回る。社会保険労務士時代に得た労働社会保険諸法令の細かな知識を活かし、かゆい所に手が届く退職代行サービスを目指して日々奮闘中。2019年に携わった労働事件(労働者側・使用者側の両方。労働審判を含む)は、60件以上となる。
TOPへ戻る