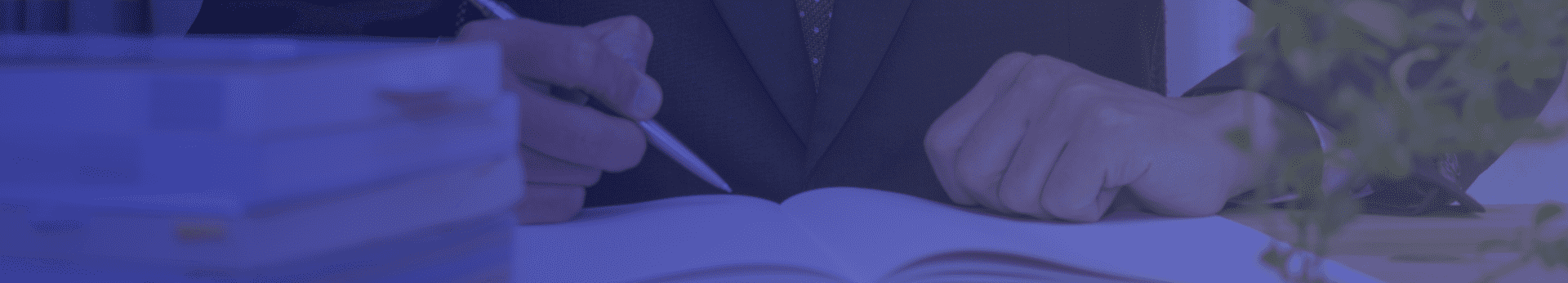
弁護士コラム
第164回
『軽貨物の業務委託の解除で退職代行を利用する方法』について
公開日:2025年9月18日
退職
弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。
退職代行を専門的にはじめて早いもので、数年が経ちました。
その間、数多くの退職代行をした経験から「これは」と思うことをコラムにします。
コラム第164回は『軽貨物の業務委託の解除で退職代行を利用する方法』についてコラムにします。
軽貨物の業務委託について退職代行のご相談、ご依頼については弁護士の退職代行からお問い合わせください。

目次
1.軽貨物運送の退職代行について
業務委託契約とは、委託者と受託者との間で委任契約に基づき契約を結んでいます。今回は、軽貨物運送の受託解除について退職代行使って数多く解除させている弁護士の清水隆久が解説します。
フリーランス新法が2024年(令和6年)11月に施行されました。私はフリーランス新法が成立されたときは、個人事業主として軽貨物運送に携わるフリーランスの方が救済されると思いましたが、実際には、まったく救済されないどころか『解除』することがより難しくなっていると思いました。
それでは、今回の内容に入ります。
個人事業主として軽貨物運送を行なっている方は、amazon、ヤマト運輸、佐川急便、などから直に受けている訳ではなく、一社入ってその一社と契約を結んでいます。二次受けになっています。
場合によっては、さらにもう一社が入っていることもあり、三次受けになっていることもあります。間に入っている会社の方が口を揃えて『個人事業主は、社長だからね。責任とってもらうよ。』といいます。
このフレーズの『個人事業主は、社長だからね。』というのは搾取をするための方便に過ぎません。
フリーランス新法の施行により前は契約書を結ばなかった業界ルールから、業務委託の契約書を結んことが当たり前になり、解除条項に制限が加えられいます。例えば、契約書がない場合には、民法第651条により解除の通知したタイミングで解除できるようになっていました。
しかしながら、現在では、60日前の解除通知を契約書で要求し、60日間の就業(稼働)を強いている規定がほとんどです。また、60日間の稼働ができない場合には、その60日間について1日あたりの違約金を設定しています。
そんな中、私は日々、軽貨物の業務委託について退職代行を行っています。解除理由は様々です。少し難しい話になりますが、民法415条の契約不履行には、『その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。』と明確に規定されています。
解除により、契約の不履行が生じる場合には、『債務者の責め帰責できない事由』を弁護士が解除先の会社に対して積極的に主張すべきです。
具体的には、『やむを得ない事実』を解除する受託者は主張することになります。会社側のパワハラであっても良いですし、体調不良でも法的に主張できるものは主張すべきです。お困りでしたら、私までご相談ください。
2.判例を紹介
次によく『偽装委託(偽装請負)の主張はできますか?』というご質問を受けます。実益として、偽装委託の主張をして実質的な雇用にあることや、その退職の主張をすることにあります。赤帽の軽貨物運送の事案ですが、最高裁があるので紹介します。
※横浜南労基署長(旭紙業)事件(最高裁第一小法廷平成8年11月28日判決)は、自らの持ち込んだトラックを運転する形態の運転手として運送業務に従事していた個人事業主の労働者性を否定しています。
①専属的に会社の製品の運送業務に携わっており、同社の運送係の指示を拒否する自由はなかったこと、②毎日の始業時刻及び終業時刻は、運送係の指示内容のいかんによって事実上決定されることになること、③運賃表に定められた運賃は、トラック協会が定める運賃表による運送料よりも一割五分低い額とされていたことなどの事実関係を考慮しても、❶労働基準法上の労働者ということはできず、(労働者災害補償保険法上の)❷労働者にも該当しないものと判断しています。
①②③をもって相談者の方は、偽装委託であると言われる方もいらっしゃいますが、最高裁である程度決着が着いています。
①②③のポイントを見てもらえれば、軽貨物運送の個人事業主は、労働者と簡単には言えません。
今回のコラムについては難しい内容が書いてあると思いますが、法的な主張が大事であるという点はわかって頂けたかと思います。
民間の退職代行会社が軽貨物の退職代行をしているケースも見受けられますが、弁護士の退職代行一択であると私は考えています。
偽装委託については第31回『業務委託契約の退職代行』について、をご参照下さい。
3.まとめ
その他として、軽貨物運送の場合には、自分の車を持ち込みするのではなく、リース車両としてリースを受けて、その車両で受託業務を行っているケースがはかなりの割合を占めます。解除時に車両事故の部分について高額な修理費用を請求されるケースもあります。
軽貨物の業務委託の退職代行にあたっては、リース車両の解除についても行うことが多いです。リース車両の解除についてもお悩みでしたら、私までご相談ください。
・参考コラム
第19回『業務委託の退職代行』について
第22回『休職代行のメリットと理由』について
・参考条文
民法
第651条第1項
(委任の解除)
委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
第658条 (準委任)
この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
弁護士法人川越みずほ法律会計の紹介
いち早く退職代行を手掛け、今までも多数の相談及び解決事例があります。
今回、その中でもご質問が多いご相談事項をコラム形式でまとめました。
この記事の執筆者

弁護士清水 隆久
弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士
埼玉県川越市出身
城西大学付属川越高校卒業、中央大学法学部法律学科卒業、ベンチャー企業経営、労働保険事務組合の理事、社会保険労務士事務所の代表を経て、予備試験合格、司法試験合格、司法修習終了後、弁護士法人川越みずほ法律会計を設立、同弁護士法人代表に就任。労務・税務・法律・経営の観点から、企業法務に関わる傍ら、東から西へと全国を飛び回る。社会保険労務士時代に得た労働社会保険諸法令の細かな知識を活かし、かゆい所に手が届く退職代行サービスを目指して日々奮闘中。2019年に携わった労働事件(労働者側・使用者側の両方。労働審判を含む)は、60件以上となる。
TOPへ戻る