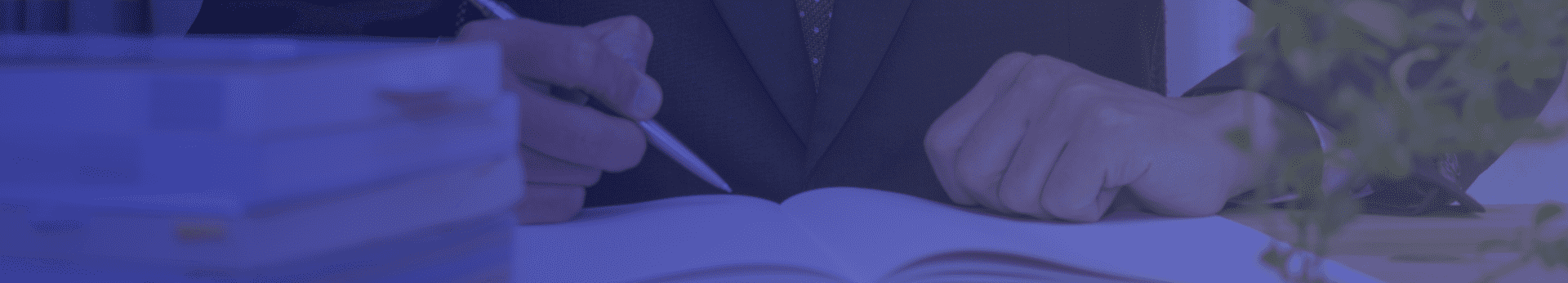
弁護士コラム
第165回
『代表社員の退任代行は弁護士が必須な理由』について
公開日:2025年9月19日
退職
弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。
退職代行を専門的にはじめて早いもので、数年が経ちました。
その間、数多くの退職代行をした経験から「これは」と思うことをコラムにします。
コラム第165回は『代表社員の退任代行は弁護士が必須な理由』についてコラムにします。
代表社員の退任代行(退職代行)についてのご相談、ご依頼については弁護士の退職代行からお問い合わせください。

目次
1.代表社員の退任時の問題点について
一般的には代表社員という言葉は聞き慣れないかもしれません。代表社員とは、①『合同会社』、②『士業』、の代表にあたる法律上の用語になります。株式会社で言うところの代表取締役と説明した方が分かりやすいと思います。社長とも言えます。
今回は、そんな代表社員の退任代行についてコラムで解説します。今回のコラムも弁護士の清水隆久が解説します。合同会社や士業の法人の代表社員になった場合でも、実質的なオーナーがいる場合で自分で退任の話をするのが難しいケースがあります。
その難しいケースとは、退任することで損害賠償の法的な問題に発展する場合が考えられます。法的責任に発展する前の段階で弁護士に相談することを強くおすすめします。それでは、具体的な内容に入ります。
実は①合同会社の代表社員の方が退任するポイントは、代表取締役の退任と違いはありません。合同会社は、株式会社の機関をミニマムにした組織であるため株式会社の代表取締役の退任代行が利用できるのは皆さんも納得ができると思います。
コラム第111回『代表取締役の退職代行(退任代行)がおすすめな理由』をご参照ください。
2.士業法人の代表社員の退任について
次に、②の士業の法人の代表社員について解説します。士業の法人とは、例えば、行政書士法人、社会保険労務士法人、税理士法人、司法書士法人、弁理士法人、弁護士法人などが考えられます。
②の士業の法人の代表社員は、業務執行について無限責任を負います。株式会社や合同会社の代表が自分の出資している範囲でしか業務執行に対する責任を負わない間接有限責任と比べてその責任の度合いは、比べものにならないぐらい差があります。代表社員の退任代行については、民法第651条に基づいて代行します。
※民法第651条によれば、『委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる』となっており、退任代行したその日が退任日となります。いわゆる『即日退任』になります。
例えば、今日付けで退任する旨を伝えれば今日にでも辞めることができます。しかしながら、第2項で『相手方に不利な時期に委任を解除したときは、相手方の損害を賠償しなければならない』とされています。
不利な時期とは、その事務処理ができない時期などを指します。先程の事例で今日付けで退任したいと言った場合には、不利な時期にあたる可能性が高いと言えます。
しかしながら、不利な時期とは、個別事情を加味しますので、極端な例であれば、あくまでも法人の代表社員は、名義だけで、実質的にその法人を切り盛りしているオーナーがいて、即座に他の登録者が代表社員になれれば不利な時期にはあたらないと言えます。
また、名義貸しの問題はありますが、一定期間、代表社員の名義を残しつつ退任時期を一定期間伸ばしてその一定期間で他の登録者を探して代表社員になってもらう方法もあります。
不利な時期については、弁護士と相談して上手くタイミングを合わせる必要があります。お困りでしたら、遠慮なく私までご相談ください。
3.損害賠償請求について
やむを得ない事由の検討について
民法第651条第2項但書によれば、『やむを得ない事由があったときは、損害賠償を負わない』とされています。やむを得ない事由について、民法第415条にも似通った文言があり、『その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるとき』と規定されています。
❶発生原因、❷取引上の社会通念に照らして、❸債務者の帰責事由にあたらないこと、がポイントになります。例えば、違法行為の強要や名義貸しの状態になっている場合、パワハラを受けている場合、継続的な体調不良などは、❶❷に照らして、❸債務者の責めに帰することができない場合にあたる場合もあります。退任時の損害賠償対応についてご心配でありましたら、私までご相談ください。
4.出資割合について
士業法人の代表社員であった場合には、出資割合を持つ必要があります。そのため、代表社員を退任するにあたっては、出資割合の精算を行う必要があります。
士業法人の場合には、社員以外の方が出資割合を持つことができません。退任代行の際には、退任と合わせて出資割合の精算を行うことがほとんどです。
5.まとめ
士業法人の代表社員の場合でも退任登記手続きについても株式会社の代表取締役の場合と同じように問題になります。
また、代表社員以外にも社員の方が退任代行を依頼する場合もありますが、今回のコラムについては、社員の方であっても使える知識となります。
代表社員、社員の方の退任登記手続きについて心配でしたら、私までご相談ください。
・参考コラム
第23回『取締役の退職代行(辞任代行)』について
第145回『取締役(役員)や理事の退任登記抹消されない場合【退職代行】』について
・参考条文
会社法第330条
(株式会社と役員等との関係)
第三百三十条 株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
民法第651条
(委任の解除)
1 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。
ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。
弁護士法人川越みずほ法律会計の紹介
いち早く退職代行を手掛け、今までも多数の相談及び解決事例があります。
今回、その中でもご質問が多いご相談事項をコラム形式でまとめました。
この記事の執筆者

弁護士清水 隆久
弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士
埼玉県川越市出身
城西大学付属川越高校卒業、中央大学法学部法律学科卒業、ベンチャー企業経営、労働保険事務組合の理事、社会保険労務士事務所の代表を経て、予備試験合格、司法試験合格、司法修習終了後、弁護士法人川越みずほ法律会計を設立、同弁護士法人代表に就任。労務・税務・法律・経営の観点から、企業法務に関わる傍ら、東から西へと全国を飛び回る。社会保険労務士時代に得た労働社会保険諸法令の細かな知識を活かし、かゆい所に手が届く退職代行サービスを目指して日々奮闘中。2019年に携わった労働事件(労働者側・使用者側の両方。労働審判を含む)は、60件以上となる。
TOPへ戻る