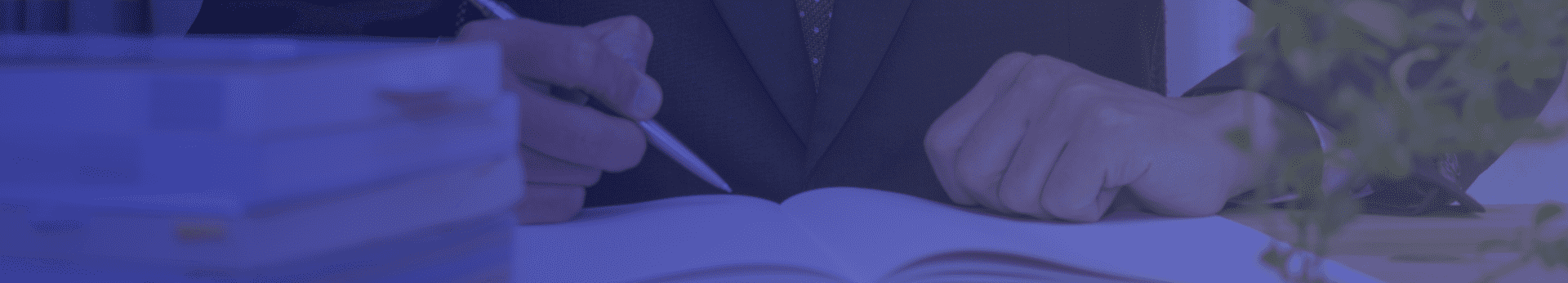
弁護士コラム
第123回
『看護師のための退職代行時の奨学金(借入金)と分割交渉』について
公開日:2025年5月29日
退職
弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。
退職代行を専門的にはじめて早いもので、数年が経ちました。
その間、数多くの退職代行をした経験から「これは」と思うことをコラムにします。
コラム第123回は『看護師のための退職代行時の奨学金(借入金)と分割交渉』についてコラムにします。
民間の病院にお勤めの看護師の方が退職代行と奨学金の返済を分割交渉を依頼したい場合は、弁護士の退職代行からお申し込みください。

目次
1.民間病院にお勤めの看護師の方について
看護師の方が病院勤務するにあたって、看護師免許取得費用を病院から借入しているケースがあります。
その借入金は、奨学金という名目になっているケースがほとんどです。
その奨学金の内訳としては、学校の入学金、授業料、生活費などになります。その奨学金の総額は、300万円を超えてくることもあります。
現在では、看護師の奨学金について、金銭消費貸借契約をした上で、5年以内に、退職した場合に返済するという契約であっても、労働基準法第16条の趣旨には反せず、適法となっています。
そこで、退職後に、奨学金の残額について退職者は返済することになります。
次に、看護師免許を取得するにあたっては、奨学金を退職に一括返済できれば、奨学金の借入金については問題が生じませんが、一括返済の資力(資金)がない場合に、退職できますか?というご質問を頂きます。
実は、奨学金の返済について一括返済ができない場合でも、退職にはまったく影響はなく、退職ができます。
民間の病院の場合、雇用期間の定めがない正職員であれば、民法第627条第1項により、退職の申し出をしてから14日経過後に退職できます。
また、雇用期間の定めがある契約職員であれば、民法第628条により、やむを得ない理由がある場合には、退職の申し出をしたその日に退職になります。
さらに、奨学金の一括返済ができない場合には、本来の返済期日を退職者が支払いできる期日に再設定することや、分割交渉の依頼を退職代行と合わせて依頼を受けることが最近では増えています。
その際、分割交渉は成功しますか?というご質問を受けますが、分割交渉し、分割に応じてもらえるかは、返済期間と返済金額次第となります。あまりにも低額な返済額では、病院側も納得しませんが、かと言って、ない袖は触れないため、病院側も、ある程度、分割の交渉に応じざるを得ません。
結局のところ期日までに奨学金の返済がない場合に、病院側が裁判して、退職者の財産に対して執行し、回収する労力は、かなりの負担となり、病院側も裁判を避ける傾向があります。よって、病院側も一般的に奨学金の分割返済に応じざるを得なくなります。
また、奨学金の借入にあたって、保証人を立てているケースがある場合には、退職者が期日までに一括返済できない場合には、保証人に対して奨学金の返済を求める可能性があります。
しかしながら、保証人に一括返済の資力(資金)がない場合には、回収をする労力から裁判自体を回避する傾向がありますので、一般的には、やはり、分割交渉に応じざるを得ません。ここまでをまとめますと、奨学金返済の分割交渉をした場合には、分割に応じるケースが多くあります。
2.公務員の看護師の方について
話は変わりまして、今回、公立病院や市立病院に勤務する看護師の方が、奨学金を借りていた場合についても解説します。
公務員の方が退職時に奨学金を返済することは、民間の病院にお勤めの方とそれほど違いはありませんが、場合によっては、返済期日が退職から1年以内となっており、返済期日に猶予があります。
そのような意味では、民間病院にお勤めの看護師の方よりは、奨学金の返済は随分と楽に感じると思います。
ちなみに、公務員の看護師の方が退職代行した場合には、年次休暇があれば年次休暇を消化し、年次休暇がない場合であっても退職代行したその日を退職日とする即日退職が認められています。
メンタルクリニックに通うなど体調が悪い場合には、病気休暇を取得することもできます。病気休暇や休職手続きについても、私が代行することもできますので、ご相談ください。
話を戻しまして、公務員の看護師であって、奨学金を借りていた場合でも退職には影響はなく、退職はできます。民間の病院に勤務する看護師の方と同様になります。
したがって、奨学金返済を心配して退職に踏み切れない看護師の方でも、退職できますので、安心してください。お困りでしたら、遠慮なく私までご相談ください。力になります。
3.まとめ
最近では、奨学金返済についてのご相談が増えてきました。看護師の方が職場でパワハラを受けていたり、上司や同僚から当たりが強いケースなどの相談を受けています。
奨学金返済が心理的な足枷となって退職に踏み込めず精神的に辛い思いをし、メンタルクリニックに通うケースもあります。体や心が壊れる前にぜひ私までご相談ください。力になれると思います。
・参考条文
労基法第16条(賠償予定の禁止)
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
民法587条(消費貸借)
消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
民法第627条第1項
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法第628条
(やむを得ない事由による雇用の解除)
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
・関連コラム
第28回『資格取得費用(研修費用)にあたって金銭消費貸借契約書を結んでいるケース』について
弁護士法人川越みずほ法律会計の紹介
いち早く退職代行を手掛け、今までも多数の相談及び解決事例があります。
今回、その中でもご質問が多いご相談事項をコラム形式でまとめました。
この記事の執筆者

弁護士清水 隆久
弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士
埼玉県川越市出身
城西大学付属川越高校卒業、中央大学法学部法律学科卒業、ベンチャー企業経営、労働保険事務組合の理事、社会保険労務士事務所の代表を経て、予備試験合格、司法試験合格、司法修習終了後、弁護士法人川越みずほ法律会計を設立、同弁護士法人代表に就任。労務・税務・法律・経営の観点から、企業法務に関わる傍ら、東から西へと全国を飛び回る。社会保険労務士時代に得た労働社会保険諸法令の細かな知識を活かし、かゆい所に手が届く退職代行サービスを目指して日々奮闘中。2019年に携わった労働事件(労働者側・使用者側の両方。労働審判を含む)は、60件以上となる。
TOPへ戻る