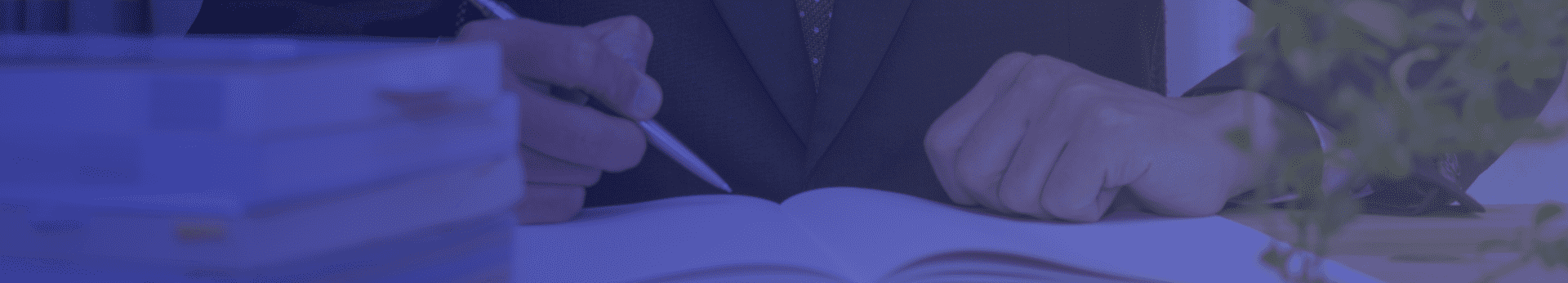
弁護士コラム
第150回
『退職代行時に効率的に有給消化や有給取得する方法』について
公開日:2025年8月19日
退職
弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。
退職代行を専門的にはじめて早いもので、数年が経ちました。
その間、数多くの退職代行をした経験から「これは」と思うことをコラムにします。
コラム第150回は『退職代行時に効率的に有給消化や有給取得する方法』についてコラムにします。
退職代行時の有給取得についてのお問い合わせは、弁護士の退職代行のページからご連絡ください。お待ちしております。

目次
1.退職代行時に効率的に有給取得、有給消化する方法
有給を取得することは、働く側の権利であると一般的には言われています。
しかしながら、権利であっても、会社側で、拒否する場合や無視する事例が一定程度あります。有給を取得するにあたって、有給の時季指定権というものがあります。時季指定権とは、有給をいつからいつまで消化するという権利を言います。
この時季指定権を上手く使うことが有給消化を効率的に行う方法になります。
より具体的な説明に入ります。
①例えば、9月1日に退職代行を行うケースで、9月の所定出勤日が20日とします。その際、有給残日数が23日あるとします。賃金の締日が末日締切とします。本来的には、全有給消化した日が10月3日になりますので、退職日を10月3日とすることも可能ですが、賃金の締日を考慮して、9月末日を退職日として、3日余った有給を放棄する方法があります。
会社としては、賃金の締日からはみ出てしまった3日の有給分については、次の賃金の締日で支給するのが手間になります。また、会社側の印象としては、一定程度、有給消化について譲歩することで、円満解決を目指す姿勢を示すことができます。
②一定程度、有給放棄をする方法は、有給残日数がはっきりしないケースでも有効です。仮に、入社から1年6ヶ月たったケースでは有給残日数は、21日が最大限となります。しかしながら、1年6ヶ月の間で、数日有給を使ったケースで、有給残日数がはっきりしなくなる場合があります。その際、少なくとも15日は残っていると仮定します。
このケースについては、民法第627条第1項と関連して考えます。民法第627条第1項にすれば、退職の申し出をしてから14日後を退職日となります。その際、退職日までの14日間を有給にあてて、消化出来なかった日数については、有給を放棄します。
このケースでの有給放棄については、14日経過後を退職日とすることで、退職日をスムーズに確定させることや、会社側での有給残日数の確定の手間を省略させる趣旨があります。
③最後のケースとしては、有給残日数が5日のケースがあったと仮定します。その際、民法第627条第1項と関連して考えます。民法第627条第1項によれば、退職の申し出から14日経過した後を退職日としますので、14日間に有給をあて、足りない日数を欠勤とさせます。
③のケースは、1番イメージしやすいと思います。
①②のポイントは、有給の時季指定権と有給の放棄になります。スムーズに理解できましたでしょうか?スムーズに理解できる=知識として使い易いということになると私は考えています。
2.退職時の有給の時季指定権、時季変更権の関係について
時季指定権と時季変更権に関係についても良く質問を受けますので、改めて解説します。
時季指定権は、上記の通り、いつからいつを有給消化や有給取得する権利になります。その一方で、会社側としては、有給を取得する時季を変更させる権利をもっています。
一般的な学術的な見解の多くは、退職時には、退職日が決まっている関係で、時季変更権は制限されるという見解を述べています。しかしながら、現在のところ、退職時の時季変更権と時季指定権の関係について判断した最高裁の判決(判例)は存在しません。
したがって、実務的には、退職時の時季変更権と時季指定権の優劣関係についてはどちらが優先されるかは決着がついていません。
以上からすれば、有給消化について会社側が拒否した場合に、労働者側から裁判をしたとしても必ずしも勝てる状況にあるとは断言できません。注意が必要となります。
・参考条文
労基法第39条第5項
使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
・参考コラム
第66回『弁護士による退職代行と年次有給消化』について
第126回『退職日の指定と退職代行』について
第135回『退職代行を使うといつが退職日になる?』について
弁護士法人川越みずほ法律会計の紹介
いち早く退職代行を手掛け、今までも多数の相談及び解決事例があります。
今回、その中でもご質問が多いご相談事項をコラム形式でまとめました。
この記事の執筆者

弁護士清水 隆久
弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士
埼玉県川越市出身
城西大学付属川越高校卒業、中央大学法学部法律学科卒業、ベンチャー企業経営、労働保険事務組合の理事、社会保険労務士事務所の代表を経て、予備試験合格、司法試験合格、司法修習終了後、弁護士法人川越みずほ法律会計を設立、同弁護士法人代表に就任。労務・税務・法律・経営の観点から、企業法務に関わる傍ら、東から西へと全国を飛び回る。社会保険労務士時代に得た労働社会保険諸法令の細かな知識を活かし、かゆい所に手が届く退職代行サービスを目指して日々奮闘中。2019年に携わった労働事件(労働者側・使用者側の両方。労働審判を含む)は、60件以上となる。
TOPへ戻る