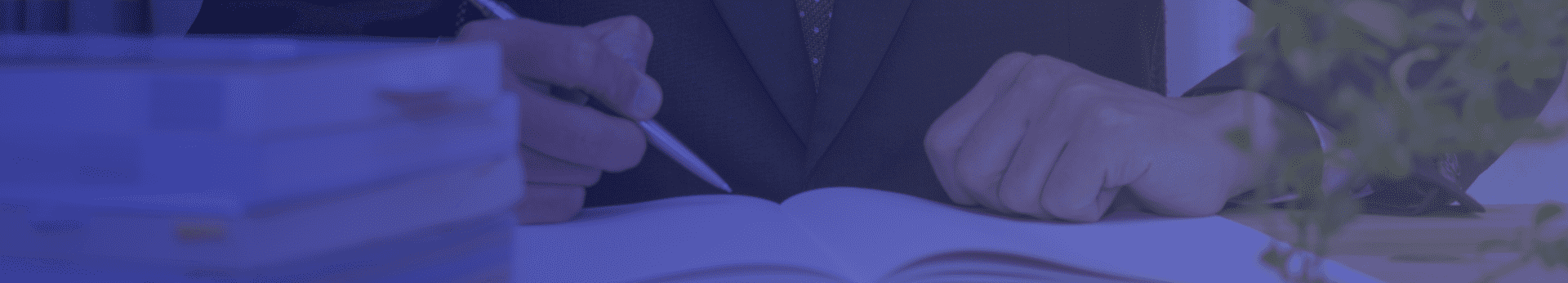
弁護士コラム
第152回
『弁護士監修の退職代行と弁護士の退職代行の違い』について
公開日:2025年8月21日
退職
弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。
退職代行を専門的にはじめて早いもので、数年が経ちました。
その間、数多くの退職代行をした経験から「これは」と思うことをコラムにします。
コラム第152回は『弁護士監修の退職代行と弁護士の退職代行の違い』についてコラムにします。
お問い合わせは、弁護士の退職代行のページからご連絡ください。お待ちしております。

目次
1.弁護士監修の退職代行サービスと弁護士が行う退職代行サービスについて
最近、某大手退職代行会社の内部告発もあり、民間企業が運営している退職代行サービスについて非弁行為にあたるのではないかという問い合わせを多くもらいます。過去、私の方では数件程度、民間の退職代行サービスの非弁該当性について裁判をしています。
その際の裁判のポイントとしては、非弁行為該当性(弁護士法72条に規定する「その他一般の法律事件」の意義)に関して次のような判断を示しました。
法的紛議が顕在化している必要まではないが、紛議が生じる抽象的なおそれや可能性があるというだけでは足りず、当該事案において、法的紛議が生じることがほぼ不可避であるといえるような事実関係が必要となっています。現状の退職代行サービスとしては、『退職の意思を伝える』だけであれば非弁行為にあたらないと言う見解になります。
それでは、ここから今回の本題になります。
弁護士監修というのは、まさに、ここの民間企業の行う退職代行サービスは、『退職の意思』を伝えるだけで、弁護士法違反にあたるような退職代行サービスを行っていないという弁護士としてのお墨付きを与えているに過ぎません。
弁護士監修であっても、監修した弁護士の方が退職代行サービスの対応をすることはなく、法的な紛争が起きる場合には、改めて弁護士に依頼する必要があります。あくまでも民間の退職代行会社ができるのは、退職の意思を伝えるだけです。
①退職日の希望(退職日の指定の希望)も言えないことがほとんどです。
②有給消化の交渉はできません。
③連絡、訪問しないで欲しいとも言えません(伝えるだけで、交渉もできません)
④損害賠償について交渉することもできません。
⑤給料の支払いがない場合に給料請求することもできません。
その一方で、弁護士自身が退職代行をしている弁護士事務所もあります。弁護士自身で退職代行している場合には、当然ながら、非弁行為にあたることもなく、交渉することができます。弁護士自身が運営している退職代行サービスは、退職代行とそれに伴う『交渉』ができます。
最近では、退職代行会社の行う退職代行サービスと弁護士自身が行う退職代行サービスでの価格面では、差はなくなっています。むしろ場合によっては、私のように退職代行会社よりも安い価格で退職代行を提供する弁護士もいます。
結論としては、弁護士監修の退職代行サービスを利用するのではなく、弁護士自身が行っている退職代行サービスを利用することが依頼者にとってメリットがあるのではないでしょうか?
某退職代行会社のyoutubeを見ていたら、就業規則では、退職の申し出から退職まで30日の期間が必要である旨の記載がされているにもかかわらず、民法では、14日間で退職できるという法的見解を民間の退職代行会社の担当が述べていました。
一般的な見解を述べるまでは、交渉していないと考えられますが、『だから14日の退職日が優先されます』と言った場合には、交渉していると評価されると考えられます。線引きが難しいと考えられます。
次に、民間の退職代行会社が、退職代行サービス時に、有給消化の話をして、その際、退職代行時に会社が有給消化を拒否した場合に、『有給は権利です』『依頼者は、有給を取りたいと言っています』『有給消化ができない場合には未払いの給料と相殺させて頂きます』と会社側に話をしているなどのケースは、交渉しているケースだと言って良いと考えます。
退職代行会社の担当としては、勢いで言ってしまうケースもあると考えております。
2.まとめ
退職代行会社が行う退職代行サービスは退職を伝えるだけにとどまり、退職に関連する交渉は一切行うことはできません。
『交渉を一切できないということ』をさらに分析すると、退職代行時に生じた交渉事その他のトラブルを労働者側に丸投げするに等しいと言え、消費者保護の観点から問題があると考えられます。
消費者契約法10条をご参照ください。
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第10条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
退職代行会社が非弁行為にあたるような交渉を行っている場合には、私までご連絡を頂けると幸いでございます。
また、退職代行会社に退職代行サービスを依頼したけれども、結果的に、退職が失敗したケースがありましたら、遠慮なく私までご相談ください。
・参考コラム
第136回『最近の退職代行サービスについての考察(弁護士法第72条違反、労働組合法)』について
第139回『退職代行した際に会社が連絡や訪問してきた場合に本人が会社に損害賠償請求ができるケース』について
・参考条文
弁護士法第72条
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
弁護士法人川越みずほ法律会計の紹介
いち早く退職代行を手掛け、今までも多数の相談及び解決事例があります。
今回、その中でもご質問が多いご相談事項をコラム形式でまとめました。
この記事の執筆者

弁護士清水 隆久
弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士
埼玉県川越市出身
城西大学付属川越高校卒業、中央大学法学部法律学科卒業、ベンチャー企業経営、労働保険事務組合の理事、社会保険労務士事務所の代表を経て、予備試験合格、司法試験合格、司法修習終了後、弁護士法人川越みずほ法律会計を設立、同弁護士法人代表に就任。労務・税務・法律・経営の観点から、企業法務に関わる傍ら、東から西へと全国を飛び回る。社会保険労務士時代に得た労働社会保険諸法令の細かな知識を活かし、かゆい所に手が届く退職代行サービスを目指して日々奮闘中。2019年に携わった労働事件(労働者側・使用者側の両方。労働審判を含む)は、60件以上となる。
TOPへ戻る