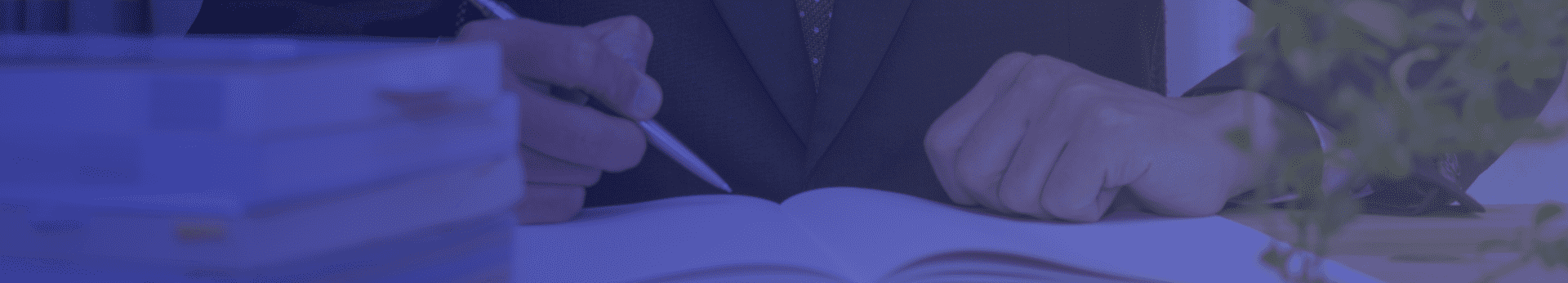
弁護士コラム
第172回
『執行役員のための退職代行サービス』について
公開日:2025年10月6日
退職
弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。
退職代行を専門的にはじめて早いもので、数年が経ちました。
その間、数多くの退職代行をした経験から「これは」と思うことをコラムにします。
コラム第172回は『執行役員のための退職代行サービス』についてコラムにします。
今回は、よく勘違いする『執行役員の退職代行サービス』について弁護士の清水隆久が解説します。
執行役員の退職代行についてご相談がありましたら、弁護士の退職代行のページからお問い合わせください。

目次
1.執行役員の退職代行について
執行役員という言葉は皆さんも聞いたことがあるかと思います。また、執行役員という肩書を会社から与えられている方も自分が法的にどのような雇用形態になっているかはわからないので教えて欲しいというご相談をよくいただきます。執行役員=役員ではありません。
役員であれば、会社と執行役員とは、委任契約が成立しているため、雇用契約とは異なります。取締役、理事、代表取締役であれば、会社法上、登記をすることが必要となります。
※会社法第915条第1項
会社において第911条第3項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。
第911条第3項
13号 取締役(監査等委員会設置会社の取締役を除く。)の氏名
14号 代表取締役の氏名及び住所(第23号に規定する場合を除く。)
委任契約については、一般的に、雇用契約より損害賠償される可能性が高くなるのが退職代行時の注意点となります。
繰り返しになりますが、執行役員というのは取締役てはないので、執行役員と会社は、委任契約ではなく、雇用契約を結んでいます。
民法第627条第1項によれば、退職の申し出をしてから14日経過後に退職することができます。
執行役員の定義自体はとても曖昧なものです。会社の部長クラスの方をあえて執行役員という名刺を与えている場合もありますし、中には、社長執行役員とう名刺を頂く場合も過去にはあります。
社長だけど登記はしませんという意味であれば、立ち位置がわからない場合もありますが、『執行役員』であること=管理者以上であることは確定しており、一般社員より仕事に対する責任は重いと言えます。そこで、退職時には、『損害賠償の可能性』について必ず検討しなければなりません。
損害賠償の内容としては、
①引継義務に反して退職した場合に発生する損害賠償
②売り上げの減少、他の従業員の時間外の増加のコスト、求人採用費のコスト
など、いくつか考えらることがあります。
損害賠償については、何度か私のコラムで解説しておりまして、コラム第115回『損害賠償対応プランと退職代行がおすすめな理由【人員要件】』について、をご参照ください。
執行役員の方が退職される場合には、私の方で事前にヒアリングします。遠慮なくお声がけください。
執行役員とは似た言葉で、『執行役』という法律用語があります。『執行役(しっこうやく)』とは、指名委員会等設置会社において、取締役会から委任を受けて具体的な業務執行の決定を行う役員です。
執行役は、会社と委任契約に基づき業務執行を行います。執行役が辞任する退職ではなく退任になります。
※会社法上の機関設計も複雑なため日本では委員会設置会社自体も少ないので、執行役という制度を導入している企業も少ないと言えます。
2.まとめ
弁護士法人川越みずほ法律会計の紹介
いち早く退職代行を手掛け、今までも多数の相談及び解決事例があります。
今回、その中でもご質問が多いご相談事項をコラム形式でまとめました。
この記事の執筆者

弁護士清水 隆久
弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士
埼玉県川越市出身
城西大学付属川越高校卒業、中央大学法学部法律学科卒業、ベンチャー企業経営、労働保険事務組合の理事、社会保険労務士事務所の代表を経て、予備試験合格、司法試験合格、司法修習終了後、弁護士法人川越みずほ法律会計を設立、同弁護士法人代表に就任。労務・税務・法律・経営の観点から、企業法務に関わる傍ら、東から西へと全国を飛び回る。社会保険労務士時代に得た労働社会保険諸法令の細かな知識を活かし、かゆい所に手が届く退職代行サービスを目指して日々奮闘中。2019年に携わった労働事件(労働者側・使用者側の両方。労働審判を含む)は、60件以上となる。
TOPへ戻る