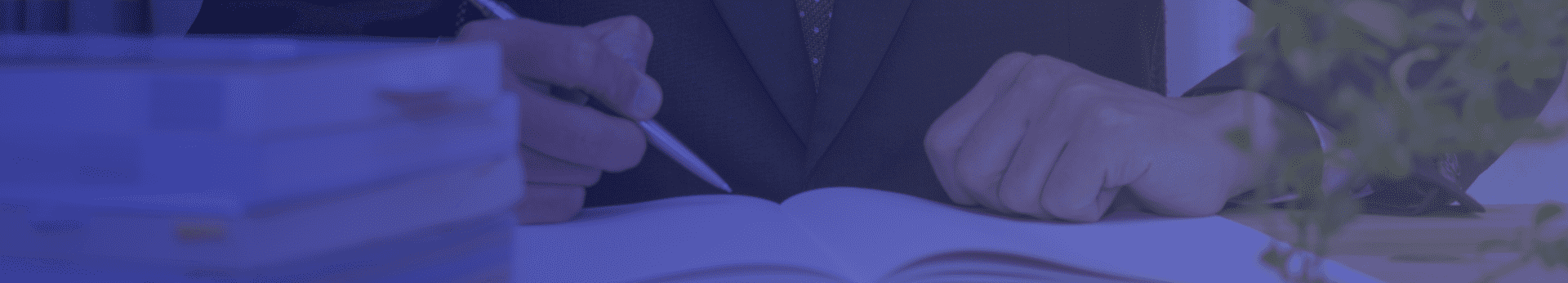
弁護士コラム
第177回
『業務委託契約(個人事業主)の退職代行サービスで
違約金が無効になるケース【相談窓口】』について
公開日:2025年10月14日
退職
弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。
退職代行を専門的にはじめて早いもので、数年が経ちました。
その間、数多くの退職代行をした経験から「これは」と思うことをコラムにします。
コラム第177回は『業務委託契約(個人事業主)の退職代行サービスで違約金が無効になるケース【相談窓口】』についてコラムにします。
個人事業主の退職代行や解除代理でご相談ががありましたら遠慮なく弁護士の退職代行サービスのページからLINE登録、または、お問い合わせを頂けると幸いございます。

目次
1.違約金の定めが無効になるメリット
それでは本題に入りまして、今回は、個人事業主が一般的に結んでいる業務委託契約の退職代行(解除代理)についても弁護士の清水隆久が解説していきます。
最近、業務委託契約の解除代理(退職代行)についてとても多くのお問い合わせをいただきます。その際、その業務委託契約は、形式的な契約であって、実態は、雇用契約(民法第623条)にあたると考えられる契約がたくさんあります。
それでは、『雇用契約』であると判断されるメリットについて次に解説していきます。
雇用契約と判断された場合には、業務委託契約の途中解約時の『違約金』の定めが労基法第16条に反して無効になることがあげられます。
さらに、自己負担とされている経費を会社に請求することや、最低賃金に反し、または、時間外手当が発生している場合の未払い賃金を請求する可能性もあります。
最近の業務委託契約の途中解除の際に、違約金が定められている契約書があることが多いため、実質的に『雇用契約』である旨の主張をすることが場合によっては重要になります。
次に実態として、雇用契約にあたるか否かについては、①から⑧で判断されるケースが多いです。①から⑧に一つでもあたれば雇用にあると判断される訳ではなく、①から⑧の総合考慮で判断されます。
①仕事の依頼、業務従事の指示等に関する諾否の自由の有無
仕事の依頼、業務指示等に対して拒否する自由がない⇒労働者性が高い
②業務内容及び遂行方法に対し指揮命令の有無
業務に対して事細かに指示命令がある⇒労働者性が高い
③拘束性の有無
勤務場所・時間が指定されて管理されている⇒労働者性が高い
④代替性の有無
代替性がない⇒労働者性が高い
⑤報酬に関する労務対償性
歩合性ではなく、一日あたりの金額で報酬が定められている⇒労働者性が高い
⑥機械器具の負担関係
業務に必要な高価な機械器具を委託元の会社側が提供する⇒労働者性が高い
⑦専属性の程度
他所の業務に従事することが制約・事実上困難⇒労働者性が高い
⑧報酬の額
同事業所の勤務する労働者と比較し、同等の報酬⇒労働者性が高い
同事業所の勤務する労働者と比較し、著しく高価な報酬⇒労働者性が低い
繰り返しますが、実質雇用契約にあたるかについては、①から⑧を総合考慮の上で判断します。
2.期間の定めがある場合
次に、『契約期間が2年と定めがあるケース』ではどのように判断されるでしょうか?
実質的に雇用契約である主張をしても『期間の定めのある雇用契約』になるため、民法第628条により、退職理由として『やむを得ない事由』が必要になります。
やむを得ない事由とは、一般的には、体調不良、給与の度重なる遅延・未払い、パワハラ・セクハラなどのハラスメントを事業主から受けていた場合がなとが考えられます。
民法第628条の雇用契約の期間の定めがある契約の退職については、コラム第129回『期間の定めのある雇用契約と退職代行』について、をご参照ください。お役に立てるコラムであると私は思っています。
3.借入金がある場合
最後になりますが、業務委託契約の退職にあたっては、勤務先からお金を借りているケースもあります。業務委託契約の解除とお金を借りて返すことは関係がないため、返済できない場合でも業務委託契約の解除をすることができます。
もっとも借入金の返済の約束については、退職時にしっかりと話合わないと後で『揉める原因』となる場合もあります。
したがって、借入金については一括で返済できない場合では、『分割での返済交渉』を弁護士に依頼することをおすすめしています。
借入金の分割については、コラム第99回『借入(借金)がある方には退職代行がおすすめな理由』について、をご参照ください。
業務委託契約の解除と借入金の分割交渉についてご相談がありましたら、私まで頂けると幸いございます。
・参考条文(民法)
民法第623条
雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。
労基法第16条
(賠償予定の禁止)
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
・参考コラム
第19回『業務委託の退職代行』について
第175回『個人事業主(業務委託)のための退職代行【相談窓口】』について
弁護士法人川越みずほ法律会計の紹介
いち早く退職代行を手掛け、今までも多数の相談及び解決事例があります。
今回、その中でもご質問が多いご相談事項をコラム形式でまとめました。
この記事の執筆者

弁護士清水 隆久
弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士
埼玉県川越市出身
城西大学付属川越高校卒業、中央大学法学部法律学科卒業、ベンチャー企業経営、労働保険事務組合の理事、社会保険労務士事務所の代表を経て、予備試験合格、司法試験合格、司法修習終了後、弁護士法人川越みずほ法律会計を設立、同弁護士法人代表に就任。労務・税務・法律・経営の観点から、企業法務に関わる傍ら、東から西へと全国を飛び回る。社会保険労務士時代に得た労働社会保険諸法令の細かな知識を活かし、かゆい所に手が届く退職代行サービスを目指して日々奮闘中。2019年に携わった労働事件(労働者側・使用者側の両方。労働審判を含む)は、60件以上となる。
TOPへ戻る