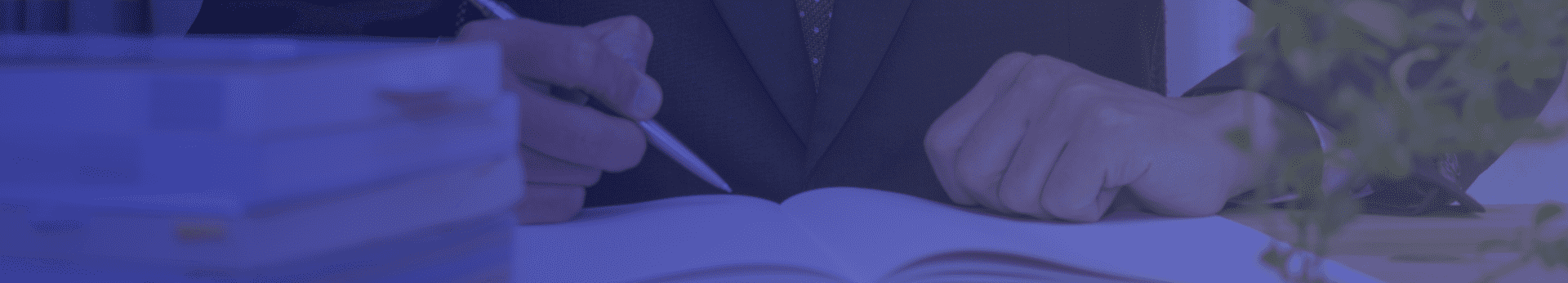
弁護士コラム
第179回
『代表取締役でも退職代行が使えるの?デメリットはないの?メリットはあるの?
【相談窓口】』について
公開日:2025年10月17日
退職
弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。
退職代行を専門的にはじめて早いもので、数年が経ちました。
その間、数多くの退職代行をした経験から「これは」と思うことをコラムにします。
コラム第179回は『代表取締役でも退職代行が使えるの?デメリットはないの?メリットはあるの?【相談窓口】』についてコラムにします。
平取締役ではなく代表取締役の退職代行を利用される方が増えています。
代表取締役の退職代行とは、正式な言葉ではなく、辞任代行という方が法律的にはしっくりきます。
※退任代行という言葉を使っているケースもありますが、退任代行と言う用語は取締役の期間満了で辞めることを『退任』といいます。
まず100%株式をもっている方が代表取締役を辞任することは、自分の会社を単に辞めることになり、自由な形で辞任することができますので、今回のコラムは、株式会社にオーナーがいて、代表取締役という肩書の雇われ社長が代行で辞任するケースをコラムにしていきます。
今回のコラムも弁護士の清水隆久が解説していきます。

目次
1.辞任代行を依頼するメリット
代表取締役の辞任代理を弁護士が行うメリットについて、①会社からの損害賠償請求の妥当性を含めて弁護士に相談ができること、②辞任手続きしない場合に裁判手続きを見据えた相談ができること、が考えられます。
①損害賠償請求の妥当性について
代表取締役と会社との契約は委任契約になっています(会社法第330条)。
委任契約については、民法第651条で、「いつでも解除することができる」となっているため、辞任の意思を伝えた日が辞任日となる即日辞任になります。もっとも、「不利な時期」に「やむを得ない事由」がない場合には、辞任について「損害賠償請求」を受ける可能性があります。
「不利な時期」とは、委任者が直ちに自分で事務の処理を開始することができず、また、他の受任者に対して事務処理を委任作成することができない時期(大審院判決大正6年1月20日)を言います。
「やむを得ない事由」の判断基準は、ケースバイケースですが、
❶代表取締役の生命・身体または精神に重大な問題が発生した場合
❷社内で暴行等を受け通常の業務遂行が不可能な状況に追い込まれていた場合
などが考えられます。
以上により、辞任代行時には、担当弁護士としては、「不利な時期」、「やむを得ない事由」の判断を代表取締役の方からヒアリングする必要があります。
②辞任手続きをしない場合について
代表取締役が辞任の意思を通知したにもかかわらず会社が辞任手続きを取らない場合には、
❸抹消登記について、裁判手続きをとる必要があります。
辞任登記の手続きをする訴訟としては、『役員辞任登記手続請求訴訟』を提起することが出来ます。
もっとも、取締役会設置会社等において辞任により取締役の最低人数に欠員が生じる場合には、新たな取締役が選任され就任するまでの間、辞任した取締役は引き続き取締役としての権利義務を有することが規定されています。
この場合には、辞任届を出しただけでは退任登記手続請求が認められませんので、裁判所に対し、辞任登記手続請求と併せて仮取締役の選任の申立てを行う必要があります。
ここまでの取締役の退職代行の流れによると、⑴辞任について、内容証明郵便で辞任の意思について、弁護士から伝える、⑵会社側で、辞任登記抹消をするように話をする、⑶会社が自主的に辞任登記抹消しない場合には、役員辞任登記手続請求訴訟を提起する。判決容認後、法務局で登記を行う。
②の手続きは以上の通りとなります。
2.辞任代行を依頼するデメリット
代表取締役の辞任手続きについて弁護士が退職代行した際のデメリットとしては、引き継ぎ時に、「会社とzoomなどで会話しなければならない」ときに、「気まずい思い」をするということがあげられます。
しかしながら、直接、代表取締役が辞任する際に、引き継ぎ事項を「書面」で行うことも沢山あるので、直接会社側と会話を行うはケースバイケースになります。
3.まとめ
弁護士法人川越みずほ法律会計の紹介
いち早く退職代行を手掛け、今までも多数の相談及び解決事例があります。
今回、その中でもご質問が多いご相談事項をコラム形式でまとめました。
この記事の執筆者

弁護士清水 隆久
弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士
埼玉県川越市出身
城西大学付属川越高校卒業、中央大学法学部法律学科卒業、ベンチャー企業経営、労働保険事務組合の理事、社会保険労務士事務所の代表を経て、予備試験合格、司法試験合格、司法修習終了後、弁護士法人川越みずほ法律会計を設立、同弁護士法人代表に就任。労務・税務・法律・経営の観点から、企業法務に関わる傍ら、東から西へと全国を飛び回る。社会保険労務士時代に得た労働社会保険諸法令の細かな知識を活かし、かゆい所に手が届く退職代行サービスを目指して日々奮闘中。2019年に携わった労働事件(労働者側・使用者側の両方。労働審判を含む)は、60件以上となる。
TOPへ戻る