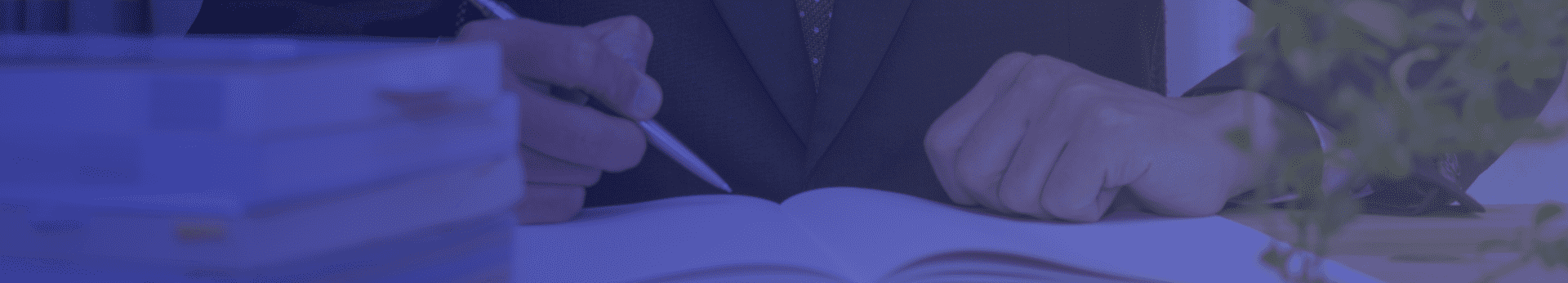
弁護士コラム
第120回
『休職代行はどんなサービスなの?使えるの?利用しやすいの?』について
公開日:2025年5月23日
退職
弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。
退職代行を専門的にはじめて早いもので、数年が経ちました。
その間、数多くの退職代行をした経験から「これは」と思うことをコラムにします。
コラム第120回は『休職代行はどんなサービスなの?使えるの?利用しやすいの?』についてコラムにします。
休職代行サービスとは、どんなサービスでしょうか?
実は、弁護士が行っている休職代行サービスと民間会社が行っている休職代行サービスとは、対応が明らかに異なります。
その違いについては、後半に明らかにしていきます。5分程度で今回のコラムは読めますので、最後までご拝読ください。
休職代行サービスの依頼の費用は、55,000円となります。
休職代行サービスの依頼はこちらからお問い合わせください。

目次
1.休職代行サービスについて
休職代行サービスとは、依頼者に代わって休職の意思を伝える(代行)することにあります。
休職代行サービスと言っても、弁護士が行う休職代行サービスは、『代理人』が行う休職代理になります。
退職代行サービスについては、かなり認知度があり、今では知らない人はいないのではないかと思います。実は、退職するというのは、重大な決断になります。
その退職という重大な決断を保留して、一旦は『お休み』をするという休職代行を私はおすすめします。
2.休職代行サービスの流れについて
休職代行サービスの流れは、弁護士が受任通知書を所属の会社に送ります。その際、弁護士が代理人として、今回の休みが正当な欠勤にあたる説明を行います。
有給残日数がある場合には、有給消化後に、休職手続きに入ります。休職手続きにあたっては、就業規則を事前に確認するようにしてください。
就業規則上に、例えば、入社から1年以内の正社員については、2ヶ月間の休職期間などが記載されているケースがあります。その2ヶ月間については、休職手続きを取ることができるので、仮に、その期間中は、会社として必ず休ませる必要があります。
会社としては、休職期間は解雇することはできませんので、休職期間中に解雇した場合には、不当解雇にあたります。
では、就業規則上、休職期間の定めがない場合には、一義的にどのぐらいの期間について休むことができるかについては、何ヶ月間の『欠勤ができるか』によります。
一般的な就業規則によれば、30日間、私傷病期間がある場合には、普通解雇ができると記載されているのがほとんどとなりますので、就業規則上、1ヶ月程度の休みの期間を取得できると考えることができます。
仮に、就業規則上、2ヶ月程度の休みが取りたいとなった場合には、会社と協議する必要があります。結果的に、2ヶ月の休みが取れない場合もあるので、注意が必要です。
3.弁護士が休職代行サービスを行うメリットについて
次に、弁護士が休職代行サービスを行うメリットとしては、会社と諸手続きについて、交渉及び協議をすることができます。会社としては、休職手続きを行うにあたっては、休職希望者でる本人と毎月の面談を求めてくることを要求してきます。
しかなしながら、休職手続きを希望する方は、『適応障害、鬱状態、うつ病』である可能性もあり、職場との面談が困難である可能性があります。
そのような場合に、弁護士が職場や会社に対して、面談については配慮義務について協議したり、拒否する交渉を行うこともあります。
そのような交渉ができるのは弁護士であればできます。仮に、弁護士以外の退職代行会社や労働組合系の退職代行会社であれば、面談の拒否や配慮義務について交渉することはできません。
4.傷病手当金申請について
休職代行サービスとセットで傷病手当金申請サポートの相談を多く受けます。傷病手当金申請とは、労務不能期間について、健康保険から平均給料(標準報酬額)の2/3が支給される制度となります。
有給消化した後の休職期間については、無給となりますので、その無給期間の所得保障にあたります。
傷病手当金申請については、所定の様式に必要事項に記入しつつ、併せて医師の意見書を貰います。
1回目の申請は時間がかかりますが、2回目以降は、スムーズに支給されることがほとんどです。
休職期間中の傷病手当金申請の注意点としては
①無給の期間について支給されること
②標準報酬日額の2/3が暦日期間(28日、30日、31日)支給されること
③労務不能期間については医師の診断が必要であること
※標準報酬日額については、直近12ヵ月分の平均標準報酬月額が26万円だった場合、
1日あたりの傷病手当金の支給金額は26万円÷30×2/3=5,780円となります。
なお、健康保険の被保険者期間が12ヵ月に満たない場合は、以下いずれかのうち低い額を算定の基礎とします。
●当該被保険者の被保険者期間における標準報酬月額の平均額
●当該被保険者の属する保険者の全被保険者の標準報酬月額の平均額
5.まとめ
実は、休職代行サービスのメリットとしては、例えば、1年間はその会社の職歴としたい場合に、しばらく会社に所属する方法として利用し、私傷病が治った場合には、復帰を見据えた形で休みを取得した場合や、失業保険を取得するために直ぐに退職するのではなく、雇用保険の加入履歴を伸ばす場合や、賞与支給日の要件を満たすために、しばらく会社に籍を置くための方法として利用する場合もあります。
私は、いずれも復職を見据えた制度あることを前提として、体調不良だから、すぐに退職するという訳でなく、一旦、休みを取り、今後の生活の不安をなくすための方法としてメリットがあると考えています。
そのようなメリットから、私は、休職代行サービスをおすすめしています。不明な点がありましたら、私までご相談ください。力になります。
・参考コラム
第3回『傷病手当金申請サポート』について
第24回『弁護士による休職代行』について
第46回『公務員のための休職代行』について
第51回『弁護士による自衛官(自衛隊員)のための病気休暇取得代行サービス及び休職代行サービス』について
第54回『弁護士による自衛官(自衛隊員)の病気休暇取得と退職代行』について
第57回『弁護士による自衛隊員(自衛官)の病気休暇期間中及び休職期間中の退職代行』について
第85回『休職期間中の退職代行』について
第89回『休職代行と退職代行の関係』について
第98回『公務員の方が弁護士に休職代行を依頼するお勧めな理由』について
第112回『休職代行時における診断書の取得方法についての解説』について
第118回『公務員(国家公務員、地方公務員)の方や民間企業にお勤めの方には休職代行(病気休暇取得代行)がおすすめな理由』について
弁護士法人川越みずほ法律会計の紹介
いち早く退職代行を手掛け、今までも多数の相談及び解決事例があります。
今回、その中でもご質問が多いご相談事項をコラム形式でまとめました。
この記事の執筆者

弁護士清水 隆久
弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士
埼玉県川越市出身
城西大学付属川越高校卒業、中央大学法学部法律学科卒業、ベンチャー企業経営、労働保険事務組合の理事、社会保険労務士事務所の代表を経て、予備試験合格、司法試験合格、司法修習終了後、弁護士法人川越みずほ法律会計を設立、同弁護士法人代表に就任。労務・税務・法律・経営の観点から、企業法務に関わる傍ら、東から西へと全国を飛び回る。社会保険労務士時代に得た労働社会保険諸法令の細かな知識を活かし、かゆい所に手が届く退職代行サービスを目指して日々奮闘中。2019年に携わった労働事件(労働者側・使用者側の両方。労働審判を含む)は、60件以上となる。
TOPへ戻る